ハートのクッキー
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ ハートのクッキー by Master ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 「ただいまー。……まだ帰っていないのかしら……」 帰宅したパティの声は、無人の部屋にむなしく響いた。 パティは、ついひと月ほど前に、マイトという名以外の記憶をなくした少年 と共に暮らすことにした。が、マイトはときどきふらりと何日かいなくなるこ とがあった。 そして今日もまた、マイトは帰っていなかった。 「……お母さんの手掛かりもないし……」 パティは生き別れの母を探していた。生活費を稼ぐためのアルバイトをしな がらの捜索は大変だったが、母に会いたい一心で、必至に情報を集めていた。 だがここのところ、まったく手掛かりすらつかめない状態だった。 「……はぁ……」 居間のソファーに座り込み、落ち込んでいたパティだったが、すぐに頭をぶん ぶんと振り、気を取り直した。 「ええい、こんなことで落ち込んじゃだめよ! ……そうだ、たしか台所に小 麦粉があったわね。マイトも帰ってくるかもしれないし……。ようし、気分転 換に……」 立ち上がったパティはエプロンを着け、台所へと向かった。 それからしばらくして。マイトは玄関の前に帰ってきた。 彼には「マイト」という名前以外に記憶がない。いや、本当はもうひとつだ けあった。それは、パティにも教えていないものだった。 「サイキッカーを倒せ……」 それが彼の全てであった。実際、気がついてから今まで、何人ものサイキッ カーを倒してきた。パティとの生活が始まってからも、それは続いていた。 行き倒れていたマイトをパティが助けたとき、マイトはパティがサイキッカー であることを見抜いた。しかし、なぜか彼女だけとは闘う気にならなかった。 それがなぜなのか、彼自身にもわからなかった。 無言のままドアを開け、玄関をくぐると、甘い香りがマイトの鼻をくすぐっ た。 「……これは……」 マイトは導かれるように、その香りの元へと向かった。そこは台所だった。 テーブルの上にバットが置かれ、そこには焼きたてのクッキーが並べられて いた。 「不思議な…… 匂いだ……」 マイトはゆっくりと手をのばし、クッキーをひとつつかむと、口へと運んだ。 「ああ! マイトったら、だめよ! まだ冷ましてるところだったのに!」 台所に戻ってきたパティは、マイトがつまみ食いをしているのを見てそう叫ん だ。 しかし、マイトは気付かないのか、惚けたような顔のままつぶやいた。 「……うまい……」 「! ……マイト……」 ようやく気付いたマイトがパティの方を向くと、彼女のまなじりに光るもの を見つけた。 「ど、どうしたんだ、パティ」 「だって……。マイトがはじめて『うまい』って言ってくれたんだもん……」 そうだった。 マイトは今までパティが用意してくれた食事も、何も言わずに食べていた。 マイトにとって、食事は単なるエネルギーを得るための手段でしかなかった。 しかし、今回は違った。こころがあたたまるような気がした。 「あ、いや、すまない。しかし、何も泣くことはないだろう」 「……もう……。そういうことはにぶいのね……」 パティはにっこりと微笑んだ。マイトもつられて笑顔になる。前にこんなふ うに笑ったのは、いつだっただろうか。 「ほら、ほっぺたにかけらがついてるよ……。子供みたいなんだから」 「あ、ああ、すまん」 「じっとしてて。取ってあげるから……」 マイトは頬に、やわらかな感触と小さな音を感じた。 こころに広がる不思議な感覚。それが、マイトが目を覚ましてからはじめて 感じた「安らぎ」だった。 Fin.
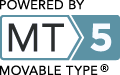
コメントする